「会社が副業禁止だけど、NISAを始めても大丈夫?」
そんな不安を抱く方は少なくありません。特にサラリーマンや公務員の方は、「投資=副業」と捉えられるのでは?と心配になるでしょう。
結論から言えば、NISA(少額投資非課税制度)は副業には該当しません。
法律上も会社規定上も、NISAは「資産運用」であり、労働の対価を得る副業とは異なります。
ここでは、なぜNISAが副業ではないのか、そして会社にバレずに安心して運用できる理由を具体的に解説します。
NISAは副業にならない
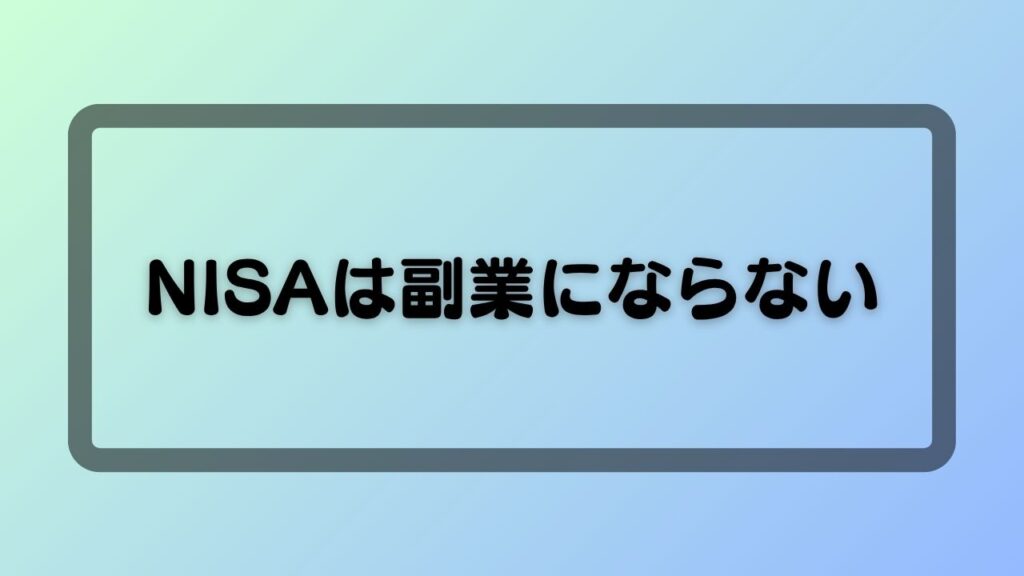
冒頭でお伝えしたように、NISAは副業に該当しません。
なぜなら、NISAはあくまで個人の資産運用で、副業の法的な定義と異なるためです。
副業の定義は、厚生労働省のガイドラインで「他の事業に雇用されて収入を得ること」または「自ら事業を行って収入を得ること」とされています。
一方、NISAは金融庁が設けた「少額投資非課税制度」です。労働ではなく、金融商品の値上がり益や配当金によって利益を得る仕組みになります。
結果、企業への就労や業務委託契約を伴わないため、副業禁止規定の対象にはなりません。
つまり、NISAは会社員でも安心して利用できる「投資制度」というわけです。
NISAを運用しても会社にバレない理由
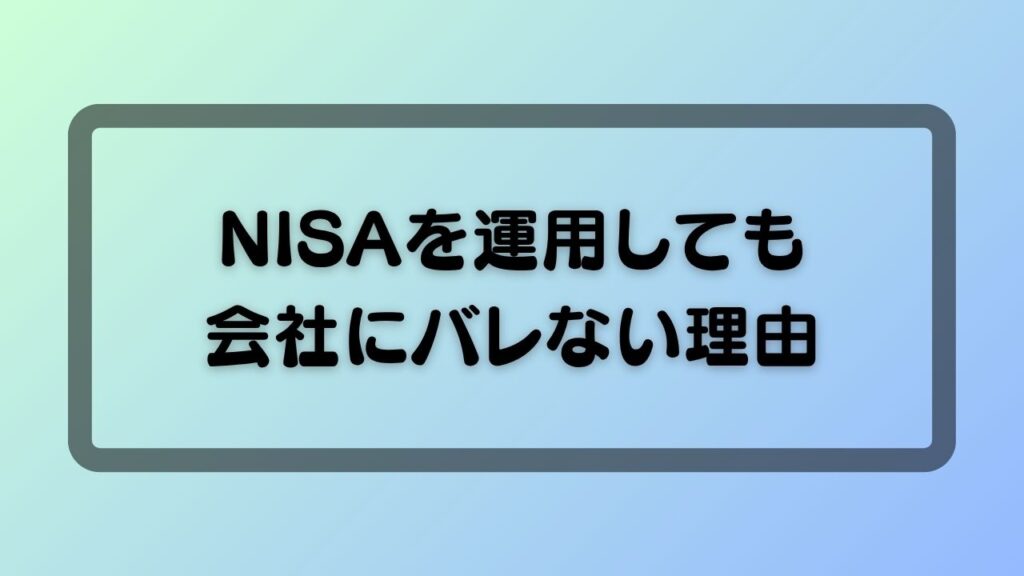
結論から言うと、NISAを利用しても会社にバレることはありません。
その理由は、税務処理や報告の仕組みにあります。
順に見ていきましょう。
報告義務がない
NISAは「副業」ではなく「資産運用」なので、会社に報告する義務はありません。
副業は労働や事業収入を得るため、雇用契約や報酬の関係で申告が必要な場合があります。しかし、NISAは自分の資金を投資に回すだけです。
そのため、勤務先に知らせる必要も、許可を取る必要も一切ありません。
また、会社とNISA口座はまったく関係がないため、運用していることが知られる心配も不要です。
会社にしてもらう手続きがない
NISAを始める際に会社を通して行う手続きが一切ない点も、バレない理由の一つです。
口座開設は、本人確認書類とマイナンバーで個人が直接行います。そして、情報を管理するのは証券会社と国税庁です。
勤務先が関与する仕組みが存在しない=会社に知られないのがNISA運用の構造なので、バレることはありません。
住宅ローンや生命保険などは勤務先の経理や年末調整で情報が確認される場合がありますが、NISAはそうした手続きとは無関係です。
非課税なので年末調整が必要ない
NISAで得た利益には税金がかからないため、年末調整や確定申告などの手続きは一切不要です。
なぜなら、NISAは国が「非課税」と定めた制度で、申告対象にならないためです。
会社が行う年末調整にもNISAの情報は関係せず、給与明細や源泉徴収票に投資内容が載ることもありません。
税金のやり取りを通して勤務先に知られる心配がなく、「税務上も完全に独立した制度」で安心して利用できる投資方法といえます。
通常の投資では利益に約20%の税金がかかり、確定申告を通じて税務署に報告する必要があります。
NISA以外の投資はバレる可能性があるので、注意してください。
副業禁止の会社でNISAを運用する際の注意点
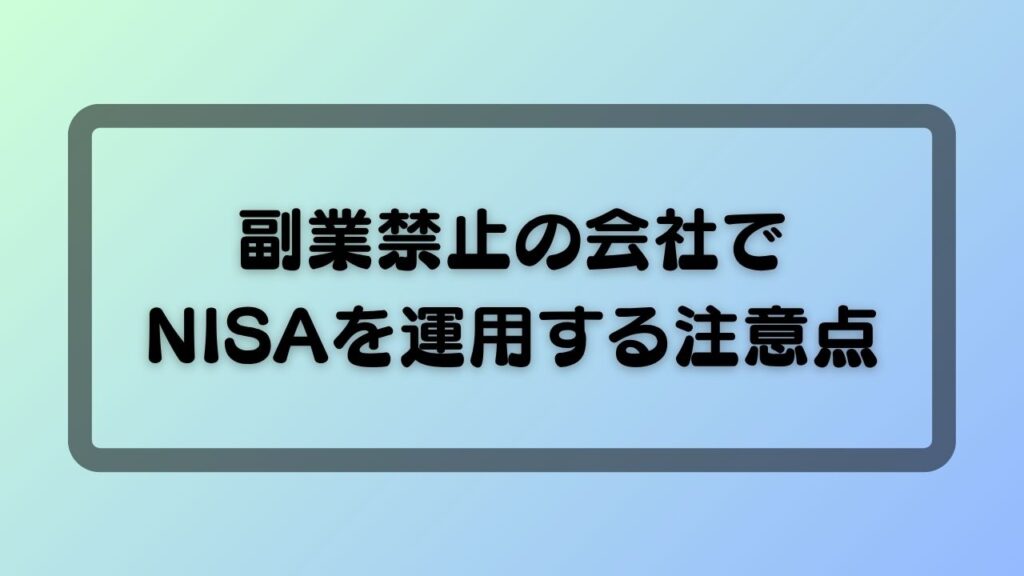
NISAが副業にあたらないとはいえ、働き方や職場での行動次第ではトラブルの原因になる可能性もあります。
ここでは、注意すべきポイントを2つ紹介します。
本業に支障をきたす行為
最も避けたいのは、NISAの運用が本業に影響を与えるケースです。
たとえば、勤務時間中に投資アプリを頻繁にチェックしたり、取引に集中して業務をおろそかにしたりする行為は、就業規則違反とみなされる可能性があります。
NISA自体は「長期投資」が基本であり、頻繁に売買する必要はありません。
短期売買を繰り返すような投資スタイルは、制度の目的にも合わないうえ、会社からの信頼を損ねるリスクもあります。
投資は勤務外の時間に、計画的に行うことが大切です。
同僚へ過度な勧誘
もう一つ注意すべきは、職場内での投資勧誘です。
「NISAはやったほうがいいよ!」と善意で声をかけたつもりでも、相手によっては営業や勧誘と受け取られ、トラブルに発展する可能性が出てきます。
NISAに限らず、 社内での金銭に関わる話題は慎重に扱わなければなりません。
NISAの話題になっても、知識を共有する程度にとどめ、投資判断はあくまで各自の責任に委ねましょう。
同僚との距離感を保つことが、結果的に自分を守ることにつながります。
金融商品取引法では「投資助言業」を無許可で行うことが禁止されています。
まとめ
NISAは副業ではないので、会社にバレる心配がありません。
非課税で手続きも個人で完結できるため、安心して資産運用を始められます。
正しく理解し、無理のない範囲で将来に備えていきましょう。
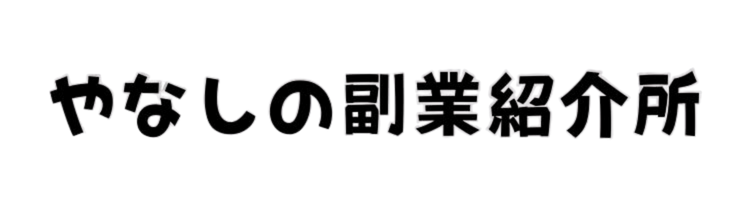
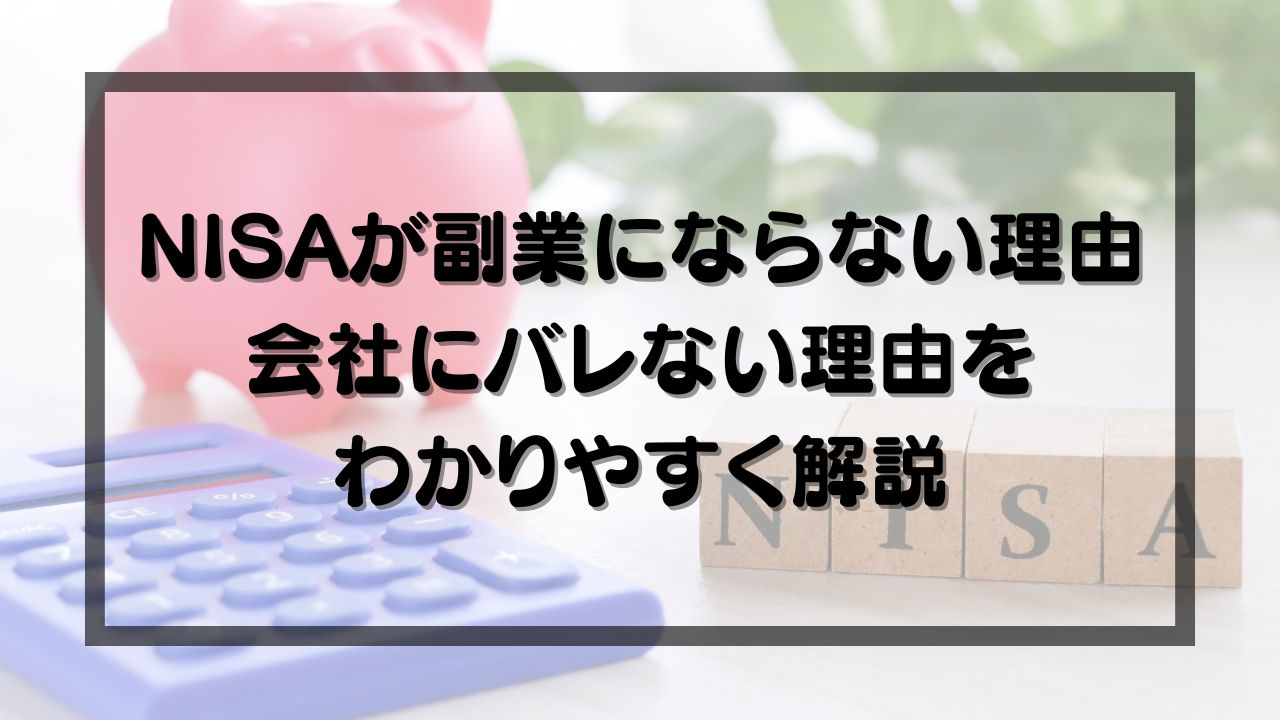
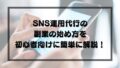
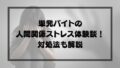
コメント